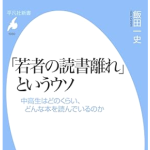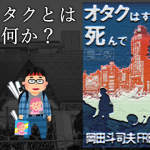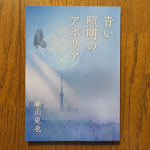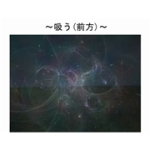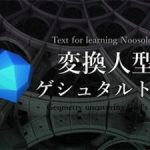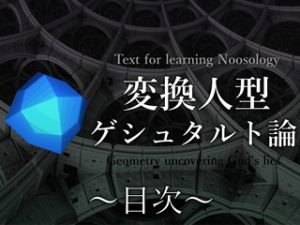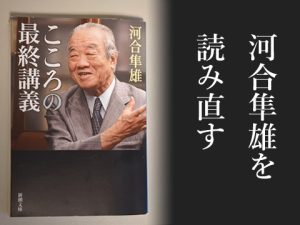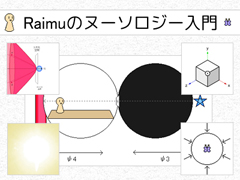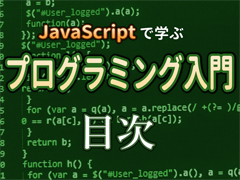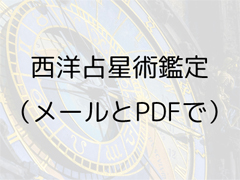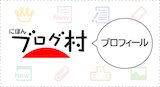『日本初! たった1冊で誰とでもうまく付き合える世代論の教科書―「団塊世代」から「さとり世代」まで一気にわかる』
・・・という書籍を読みました。
Amazonより引用すると以下みたいな内容です。
ありそうでなかった! 日本人が大好きな「世代論」の教科書!
「団塊世代」から「さとり世代」まで、「全エッセンス」を日本で初めて1冊にまとめました!
《「あなたの世代」がわかる!》
●団塊世代=60代(1947~51年生まれ)
●ポパイ・JJ世代=50代半ば~60代前半(1952~60年生まれ)
●新人類世代=50歳前後~半ば(1961~65年生まれ)
●バブル世代=40代半ば~後半(1966~70年生まれ)
●団塊ジュニア世代=30代前半~40代半ば(1971~82年生まれ)
●さとり世代=20代前半~30代前半(1983~94年生まれ)
そんな感じで、それぞれの世代の特徴についてが書かれていたので、
その内容をざっくりとまとめてみました。
各世代の特徴を箇条書きまとめ
1947~1951年生まれ『団塊世代』
・とにかく人数が多く競争が激しい
・第一次テレビっ子
・高度経済成長期を作り上げる一方で、欧米文化を取り入れた革新的な動きもある
・封建性と革新性の共存
・ビートルズが来日
・1960年代のアメリカでヒッピーカルチャーが登場
・時代の中心になりたい
・学園紛争などがあった
・1960年代後半にアメリカで女性解放運動が勃発。
ただ、日本では専業主婦にならざるを得ないのは変わらず
・女性の活躍は影ながらに
1952~1960年生まれ『ポスト団塊世代』
・学園紛争の終わり
・シラケ世代と呼ばれることもあり
・大学進学率が4割に到達
・大学では「楽園キャンパス」を始めてエンジョイする傾向になる
・インベーダーゲームやYMOなど電子コンテンツの登場
・ウォークマンの発売
・少年ジャンプ創刊。オタク第一世代の登場
・女性の活躍が表舞台にいく流れに(その後、だんだんと進んでいく)
・娯楽コンテンツが多様化していく流れに(その後、どんどん多様化していく)
1961~1965年生まれ『新人類世代』
・1980年代半ばに入社した社員に対して使われた
「新人類」という言葉が流行語大賞になる
・前の世代が持ってるイデオロギーや、思想の呪縛から解放される
・右翼や左翼など関係ない行動がされるようになる
(むしろそれ以前は右翼か左翼かにならねばならぬような呪縛があった)
・1984年に『逃走論―スキゾ・キッズの冒険』(浅田彰)などがヒット
・哲学的なものが注目される一方で、「楽しければ良い」という流れもあり
・ウォークマンの発売が中学生ぐらいにある
・ヤマト、ガンダムなどのアニメが放映。オタクが増える流れに
・1986年に男女雇用機会均等法が施行
・あと、1960年代といったらヒッピーカルチャー全盛期。
ポストヒッピー時代も続いていく
1966~1970年生まれ『バブル世代』
・1980年代後半にバブル到来。91年に破裂
・正社員には苦労なくなれた
・消費欲が強い
・自分を大きくみせる傾向あり
・ブランド志向教育ママが多い?
・男女雇用機会均等法施行後の世界で、女性の生き方は多様化していく流れに
1971~1982年生まれ『団塊ジュニア世代』(と氷河期世代)
・標準世帯が定着した頃に生まれる
・バブルがはじけて就職氷河期に突入(大体1993年から2005年)
・1970年〜1982年はだいたい「氷河期世代」とも呼ばれる
・1970年代後半生まれがとくにキツい(1983年生まれはようやくマシに)
・同世代の人口は多め
・賃金格差が広がり「勝ち組」「負け組」というワードが出てくる
・ブラック企業が問題になる
・自己啓発、自分探しが流行る流れあり
・就職はヤバくなったが、親がそこそこ裕福で文化は充実していた
・1983年にはファミコンが登場
・CDといった音楽器具も発展
・人数がそこそこ多いので企業のマーケティングのターゲットになる
・IT起業家の登場
・インターネットの始まりの文化がこの辺りから登場
・この頃からITバブルに該当するものがぼちぼち出てくるようになる
・この時代にもまた封建性と革新性の共存があったと言える
・草食系男子みたいなのも登場してくる流れになる
1983~1994年生まれ『さとり世代』
・モノをあんまり買わない世代とか言われるアレ。
書籍『欲しがらない若者たち』を語る2chスレ発祥の言葉らしい
・一昔前はだいたい「若者」にカテゴライズされてた人ら?
(けど、だんだんとそれも古くなりつつある)
・少子化世代であり数は少なめ
・氷河期はマシになる
・不景気しか知らない
・氷河期後の世界のため、年功序列制度や企業への信頼が低くなり、
会社や上司に嫌々付き合って仕事をするメリットが少なくなる
・リーマンショック直撃もあった
・金がない状況なので消費傾向は減り、節約傾向が増える
・オウム事件の勃発により宗教カルチャーが崩壊する。
一方でコンピューターが発展していく
・インターネットがどんどん普及する
・携帯電話も普及する
・後半になるとスマホやSNSも普及していく
・インターネットの登場により、テレビ離れはどんどん進んでいく流れになる
・1990年代後半に学級崩壊がメディアで取り上げられたらしい
・恋愛事情は芳しくない
1995年~生まれ
・欧米での呼び方で「Z世代」と呼ばれる
・1995年生まれは2020年にはもう25歳になっているので、
2020年時点で25歳以下の人達が該当することになる
・2008年に日本でiPhoneが登場
・スマホやSNSの普及後の世界を生きる
・2011年に311が発生する
・メディアの雑多さや偽情報が露わになってくる
・テレビへの信頼はどんどん離れる傾向にありそう
・Youtubeによる広告事業が始まり、ヒカキンなどのヒットYoutuberが登場していく
だいたいの流れ
これまでを踏まえて、だいたいの流れを書いていきましょう。
まず、経済的な流れは・・・
[戦後復興で一致団結]⇒[高度経済成長期!]⇒[一方でマルクス支持の学園紛争もあり]⇒[オイルショックなどあったが景気は上向き]⇒[バブル登場]⇒[バブル崩壊]⇒[就職氷河期]⇒[氷河期後の世界。年功序列制度ベースの既存の生活モデルの信頼が崩壊]⇒[ITバブルでのワンチャンはあるかも]⇒[ITの変化は激しくワンチャンも無くなったかも]⇒[2010年代の経済へ]
って感じ。
カウンターカルチャー的な流れは・・・
[高度経済成長への反発あり]⇒[ロックカルチャーが盛り上がる]⇒[アメリカのヒッピーカルチャーやニューエイジのジャンルが伝わる]⇒[新人類世代で思想の呪縛から解放される]⇒[オカルトブームが来る]⇒[精神世界ジャンルが流行る]⇒[新興宗教も流行る]⇒[オウム事件で崩壊する]
って感じ。
デジタルカルチャーやオタクカルチャー的な流れは・・・
[インベータ―ゲームやYMOが先駆け]⇒[アニメや漫画が徐々に普及]⇒[ファミコン登場]⇒[家庭用ゲーム機がどんどん発展]⇒[インターネット登場]⇒[インターネット環境がどんどん充実]⇒[完成されたSNSや動画コンテンツが登場]⇒[スマートフォンが登場]
って感じ。
あと、テレビも一種のテクノロジーで・・・
[娯楽といったらテレビが一番!]⇒[インターネットの登場で下火に]
になったと言えるでしょう。
女性の生き方の変化は・・・
[アメリカで女性解放運動]⇒[とはいえ日本では専業主婦が主流]⇒[女性の社会進出]⇒[男女雇用機会均等法が施行]⇒[さらに女性の社会進出]⇒[もっと女性の社会進出]⇒[とはいえ経済的にキツい時代になり、悩む女性も多そう]
って感じだと思います。
以上。これまでを踏まえて今の時代の特徴を言うと・・・
・バブルがあったのはとっくの昔
・年功序列制度への信頼感が死んだ
・宗教が死んだ
・デジタルカルチャーの発展
・インターネットの発展
・テレビの時代は終わり気味
・女性の生き方の多様化
あたりが挙げられると思います。
自分的な所感。その1
以下、自分(Raimu)の個人的な所感を書いていきます。
自分は先の本で言うと・・・1987年生まれなので『さとり世代』に該当する人間ってことになります。
自分が生きてきた実感として、兄が1980年生まれだったこともあり、1980年生まれ辺りからまたかなり時代が変化していった印象があります。
なので大体1980年生まれから先の人の方が時代感覚を共有しやすい気がします。
1980年生まれというと小学生の頃からファミコンをやってるファミコン世代で、中学生の時に『新世紀エヴァンゲリオン』が始まり、高校生の時に発展途中のコンピューターに触れ、大学生の時にブロードバンド通信が普及していて、パソコンやインターネットが自在に扱えるようになります。
インベーダーやYMOに始まる電子カルチャーや、漫画やアニメによるオタクカルチャーが、ファミコンや少年ジャンプ黄金期でどんどん発展して、さらにインターネットまでいよいよやってきたという感じです。
自分ぐらいの生まれだと小学生の頃にポケモンが登場し、中学性ぐらいでブロードバンド通信が普及して、家でパソコンが自在に扱えるようになります。
この辺りの世代の中心にあるのはやはりコンピューターやインターネットであり、コンピューターやインターネットによってコンテンツの多様化が起きて、コミュニケーションの在り方もそこから変化したと言えます。
その辺の話になると色々と書けることがありますが・・・
以下の記事で自分なりの分析をちゃんと書いたことがあります。
あと、以下の書籍でかなり的を得たことが書かれてるのでオススメです。
しかしながら、『さとり世代』の次にあたる1995年生まれは現時点(2020年)ではもう25歳で、そっちが新世代みたいな世の中にもなって来ました。
小学生の時にインターネットが自在に使える社会というのは自分でもよく分からないので、正直どうなっているのやらって感じです。
自分的な所感。その2
ちなみに、1980年代の話だと、以下の記事を書きました。
1960年代のアメリカにあったヒッピーカルチャーでは、
「マオイスト的な農本主義=人民公社=パブリックコミューンの形成、環境運動や動物愛護、自然食、LSD、マジックマッシュルーム、マリファナ擁護にくわえて、道教(タオイズム)やヨガ、インド哲学、仏教などいにしえの東洋へと思想」
・・・といったものが盛り上がっていて、
それが1980年代の精神世界ジャンルに繋がるようになっていて、それらのものが今よりももっと流行っていたみたいな話です。
大体、スピリチュアルやオカルトというジャンルも本来はその辺と繋がっています。
この辺にあったオカルトブームや精神世界ジャンルは個人的に興味のあるジャンルだし、
「自分探し」の潮流へと行きたい人はその辺りに興味を持つと良いでしょう。
しかしながら、1995年に起きたオウム事件によってそうした精神世界系のジャンルが崩壊するようになり・・・
さらに2000年代に入って、社会を取り巻く状況が経済的にもどんどん厳しくなっていきます。
人間は余裕が無くなると、生きていくために本来の自分ではない他者になるような、
「他者化していくこと」が余儀なくされます。
社会情勢が厳しくなると、とりあえず自分自身が生き残ることや、生きるためのプライドを守ることが最優先みたいになっていきます。
とはいえ、そうした「他者化の流れ」は、昔の時代からあったものなので、今の時代が特別「他者化していく時代」だとは自分は思いません。
2000年代が進み、2010年代が進み、それもぼちぼち終わりそうで、そうした中で経済的な余裕が出てきた人もいれば、社会に対する信用を失って自分探しに向かう人もいたでしょう。
今の時代にはインターネットがあり、これはよくも悪くも他者の情報に翻弄される流れもありますが、古い体制に依存しないで情報を得ることができる強みがあるし、SNSをリアルコミュニケーションに繋げれば、リアルで気の合う人同士での連携もできます。
団塊の世代にあったと言われる封建性と革新性の共存というものは、いつの時代もどこかに潜んでいるものだと思います。
そして、革新性の方が発芽していくことによって、状況が変化していきます。
・・・とはいったものの、最近の時代になると、精神世界やオカルトや、科学で証明できないスピリチュアルや、理解の難しい哲学など、抽象的でかつ難易度の高いものを使った「自己探求」に興味を持つ人がめっきり減ったように思います。
1960年代からヒッピーカルチャーが始まり、そこから続くようにオカルトブームや精神世界ブームが存在していたのは、高度経済成長期による経済基盤があった戦後の日本にしかないぐらいかなり特殊な状況だったのかもしれません。
そうしたものの流行がとても少なくなったのは、個人的には不満に思うので、古き良きものは復興されて欲しいものです。
・・・以上。色々と書いていきましたが、
こうした世代論を俯瞰してみると、
色々と見えてくるものがあって面白いと思いました。